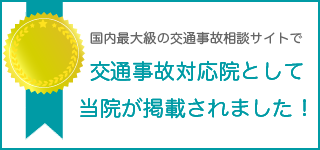顎関節症について
顎関節症(がくかんせつしょう)は、顎の関節や周囲の筋肉に異常が起こり、痛みや動きの制限を考える疾患です。日常生活での咀嚼、会話、表情の形成など、重要な機能にこのページでは、顎関節症について、種類、発生機序、症状、合併症、治療法について詳しく説明します。
顎関節症の種類
顎関節症は、病状に応じて以下の3つに分類されます。

- 筋障害型(筋膜性疼痛)
咀嚼筋や顎周囲の筋肉に異常があり、筋肉の緊張や炎症が原因で痛みが発生します。ストレスや噛み締めの癖が引き金となることが多いです。 - 関節障害型(関節円板障害)
顎関節内の関節円板が正しい位置からずれることにより、飲酒時のクリック音(カクンという音)や開閉口の制限が見られるものです。 - 変形性関節症型
顎関節に負担がかかることで、関節軟骨が摩耗・変性し、骨の変形が起こっている状態です。高齢者に多く見られますが、若年層でも発生する可能性があります。
顎関節症の発生機序
顎関節症は、多因子性の疾患であり、以下のような問題が絡んで発生します。
- 物理的要因
噛み合わせの異常(不正咬合)
一人一人で噛む癖や歯ぎしり
長い間の硬いもの咀嚼 - 心理的要因
ストレスや不安による咀嚼筋の緊張
睡眠中の歯ぎしりや噛み締め癖(ブラキシズム) - 外傷
や顎顔に対する直接的な衝撃
長時間の悪い姿勢(例:スマートフォンやパソコンを使う際の前屈姿勢) - 加齢や全身疾患
関節軟骨や骨の劣化
リウマチや関節炎などの疾患
顎関節症の症状
顎関節症の主な症状は以下の通りです。
- 顎関節や周囲の痛み
摂取時や咀嚼時の顎の痛み
耳の前部からこめかみ、首筋にかけての痛み - 関節音
口や閉口時に「カクン」「ミシミシ」という音が鳴る
大きい場合には関節円板のズレが疑われます - 開閉口障害
口が大きく言えない(口障害)
顎が最もるような感覚(顎のロック現象) - その他の症状
咀嚼筋の疲労感や緊張
頭痛や耳鳴り、肩こり
顎関節症との合併症
顎関節症が進行すると、以下のような合併症が発生する場合があります。

- 慢性的な痛み
顎周囲の筋肉や関節に炎症が持続し、慢性痛に発展する可能性があります。 - 関節変形
正しく治療されない場合、顎関節が変形し、追加機能障害を考慮します。 - 全体的な影響
顎の不調が原因で、頭痛や肩こり、姿勢の不調など全身に広がる問題を考えてございます。 - 心理的影響
ふとした痛みや顎の機能障害が、ストレスや不安感を増加させることがあります。
当院での顎関節症の治療法
当院では顎関節症の治療として、自然治癒力を引き出し、痛みを並行する手法を採用しています。主に以下の治療法をおすすめしています。
- 鍼(はり)治療
鍼を使って顎周囲の筋肉の緊張を緩め、血流を改善します。痛みの軽減だけでなく、顎の可動域の改善も期待できます。 - 電子温灸
専用の温熱機器を用いて、顎関節や周囲の筋肉を温める治療法です。 筋肉をリラックスさせ、痛みを感じる効果があります。 - 筋肉の調整
顎周囲の筋肉や咀嚼筋に対する手技療法を行い、緊張やこわばりを改善します。噛み合わせのバランスを調整することで、顎関節への負担を軽減します。
これらの治療法は、痛みの緩和だけでなく、再発予防にも効果的です。
顎関節症の予防とセルフケア
顎関節症を予防し、症状を軽減するためのポイントを以下に挙げます。
- 日常生活での注意
考えて平等に噛むことを意識する
長時間のスマートフォンの使用や前屈姿勢を気にする
ガムや硬い食品を控える - ストレスケア
リラクゼーション法(ヨガや深呼吸など)を取り入れ、筋肉の緊張を解消します。 - 定期的なメンテナンス
顎に違和感を感じたら早期に医療機関を受験する
マウスピースの装着や理学療法を習慣化する
顎関節症は、生活習慣やストレス管理の症状で緩和できる場合が多い疾患です。顎の不調にお悩みの方は、ぜひご相談ください。