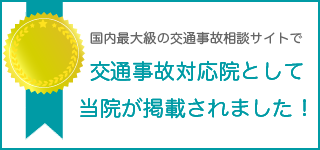後遺症の片麻痺とは?
片麻痺(かたまひ)は、主に脳卒中(脳梗塞や脳出血)の後遺症として、体の片側に麻痺や運動力低下が起こる状態を指します。
この症状は、脳の神経が損傷することで機能に影響を与え、日常生活に大きな困難をきたすことがあります。
このページでは、片麻痺の原因、症状、治療法、そして長時間の施術について詳しく解説します。
当整骨院が考える片麻痺の原因
片麻痺の主な原因は脳卒中による脳の損傷ですが、その他にもいくつかの課題が関連しています。

- 脳梗塞
脳の血管が出現し、血流が途絶えることで脳細胞が壊死し、運動機能を司る神経が損傷されることで発症します。 - 脳出血
脳内の血管が激しくて出血が起こり、周囲の神経組織が圧迫されることにより麻痺が発生します。 - 脳腫瘍や外傷
脳に腫瘍ができたり、外傷によって神経が損傷される場合にも、片麻痺が生じることがあります。 - その他の要因
・脳炎や髄膜炎などの感染症
・脳血管奇形
・神経変性疾患(例:多発性硬化症)
片麻痺の症状
片麻痺の症状は、損傷を受けた脳の部位の程度やによって異なります。以下は主な症状です。
- 運動機能の低下
・筋力低下:右側の手足に力が入らず、無理になる。
・麻痺の程度:完全に実行不可能な「完全麻痺」と、一部の処理可能な「不完全麻痺」に分けられます。 - 痙縮(けいしゅく)
筋肉が緊張して緊張し、関節が固まる状態。 特に腕や脚に見られ、手が制限されます。 - 感覚障害
触覚や痛覚、温度感覚が鈍くなる場合があります。
片方が「重い」「しびれる」と感じることもあります。 - 協調運動障害
複雑な動作やバランスが取りづらくなり、歩行や日常動作に支障をきたします。 - その他の症状
・言語障害:脳の言語中枢が損傷した場合、言葉を話す、理解する力が低下します。
・視野障害:視野の半分が見えにくい「半側空間無視」が起こる場合があります。
一般的な片麻痺の治療法
片麻痺は、リハビリテーションや適切な治療を行うことで、機能回復や生活の質を向上させることが可能です。

- 急性期治療
・血流再開治療:脳梗塞の場合、血管内治療や血栓溶解薬(t-PA)を使って血流を再開します。
・出血:脳出血の場合、止血や外科的な手術が行われます。 - リハビリテーション
・運動療法:専門家の指導のもと、筋力や関節の動きを回復させるトレーニングを行います。
・作業療法:日常生活での動作(食事や交換)を改善するための練習。
・言語療法:言語中枢が損傷された場合には、話す・聞く能力の改善を目指します。 - 薬物療法
筋肉の緊張を緩める薬や、神経伝達を改善する薬を使います。 - 先進的治療
・ボツリヌス療法:知覚縮みが強い場合には、筋肉の緊張を緩和するための注射が行われます。
・脳刺激療法:リハビリと併用することで、神経の再生を問います。
当整骨院での実際の片麻痺施術
とりあえず、片麻痺に対する自然治癒力を高める治療を提供し、症状の緩和と機能回復を目指しています。
- 鍼治療
鍼を用いて、麻痺部位やその周辺の血流を促進します。また、神経伝達の回復をサポートし、感覚的な緩和を図ります。 - 電子温灸
温熱による治療で、筋肉をリラックスさせ、心地よい縮みやこわばりを軽減します。痛みの緩和にも効果的です。 - 筋肉と関節の調整
硬直した筋肉や関節を手技療法で丁寧にほぐし、動きの改善を訴えます。 特に、知覚縮小による可動域制限の改善を目的としています。 - リハビリ支援
とりあえず、患者様ある程度の症状に合わせたリハビリメニューを提案し、専門的な指導を行います。日常生活動作の向上を目指します。
片麻痺と向き合うために
片麻痺の回復には、正しい治療だけでなく、患者様やご家族の積極的な取り組みが必要ではありません。
- 日常生活の工夫
片手で可能な動作を増やすため、リハビリで習得した技術を積極的に活用しましょう。
自助具(スプーンや箸など)を活用して、生活の負担を軽減します。 - 定期的なメンテナンス
片麻痺は一瞬のケアが必要な場合が多いです。施術を続けることで、症状の悪化防止や再発予防につなげることができます。
片麻痺は適切な治療とリハビリ、機能の一部が回復し、生活の質を向上させることが可能です。片麻痺でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。